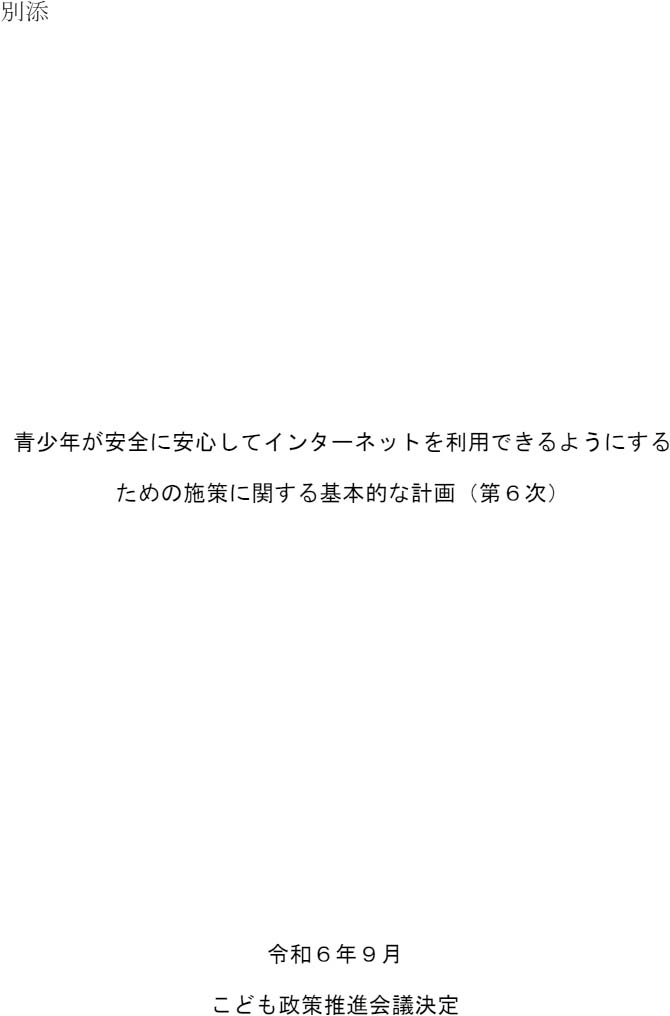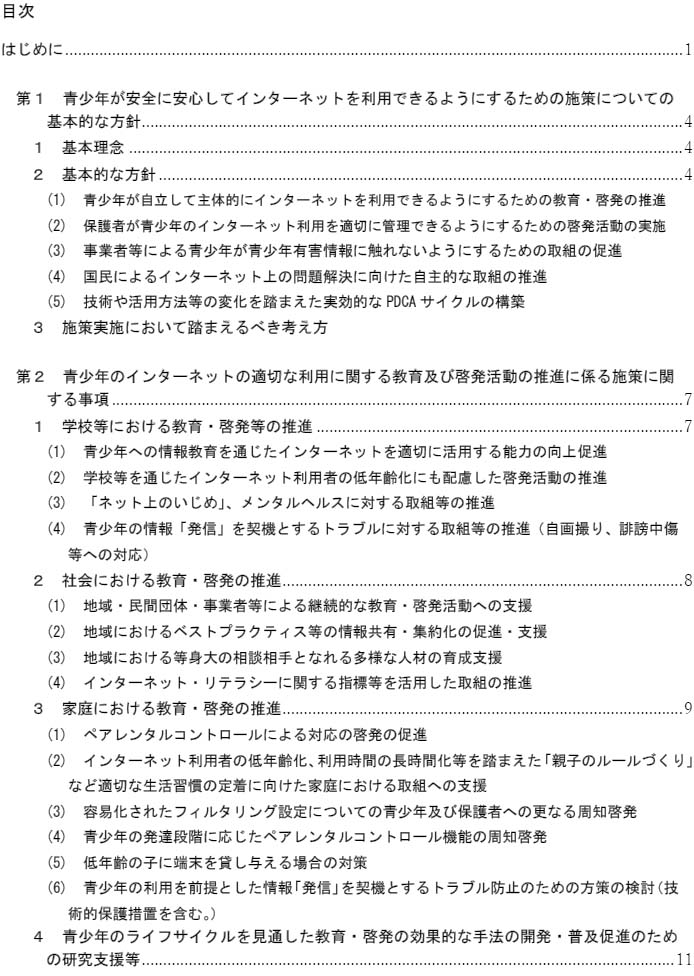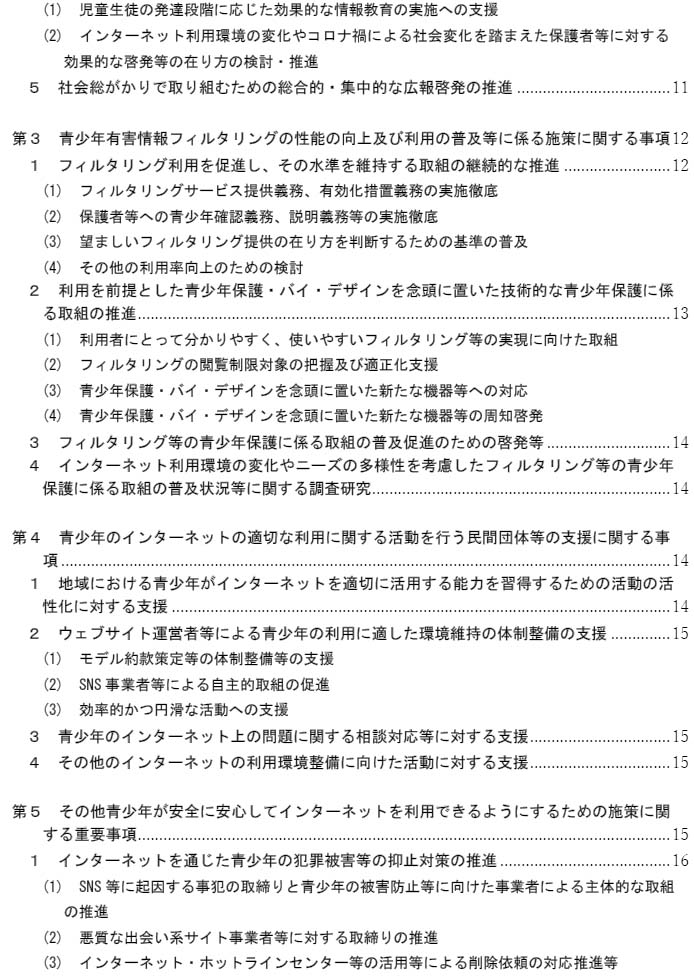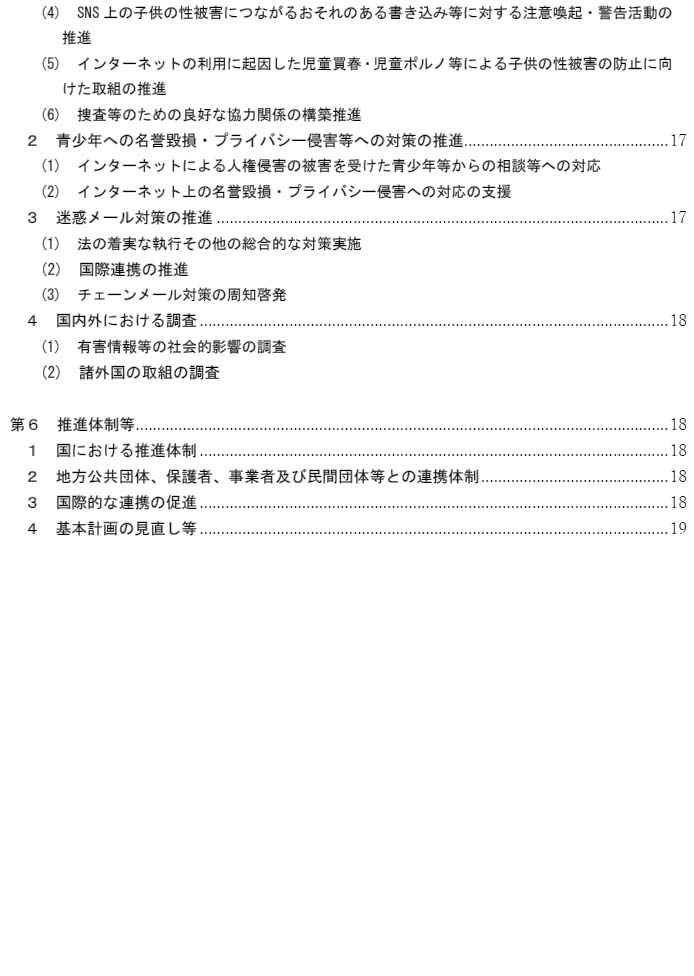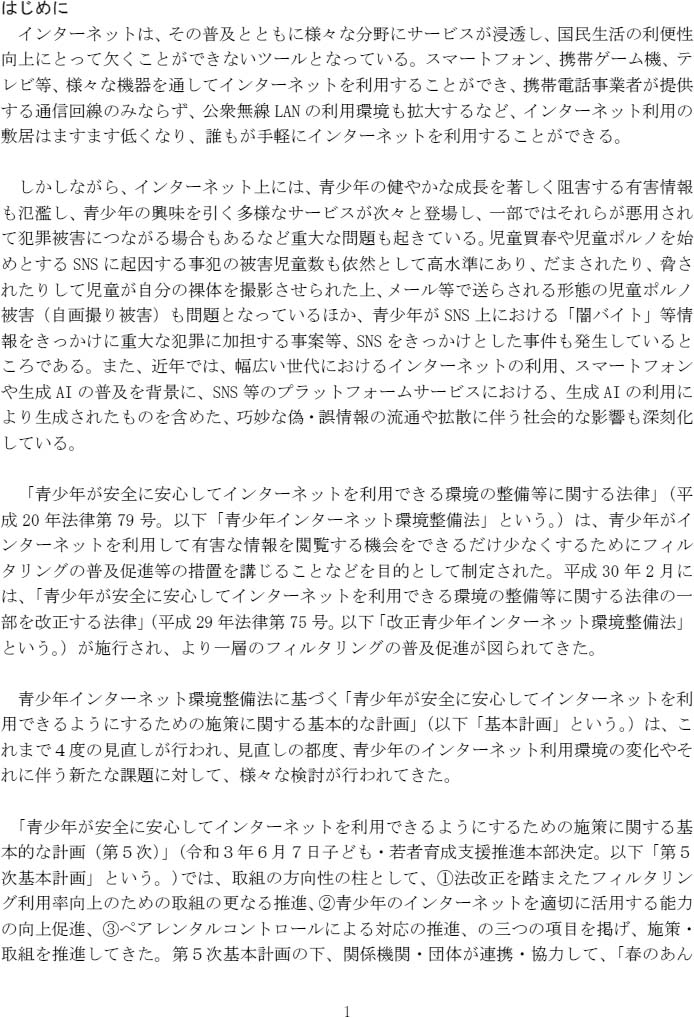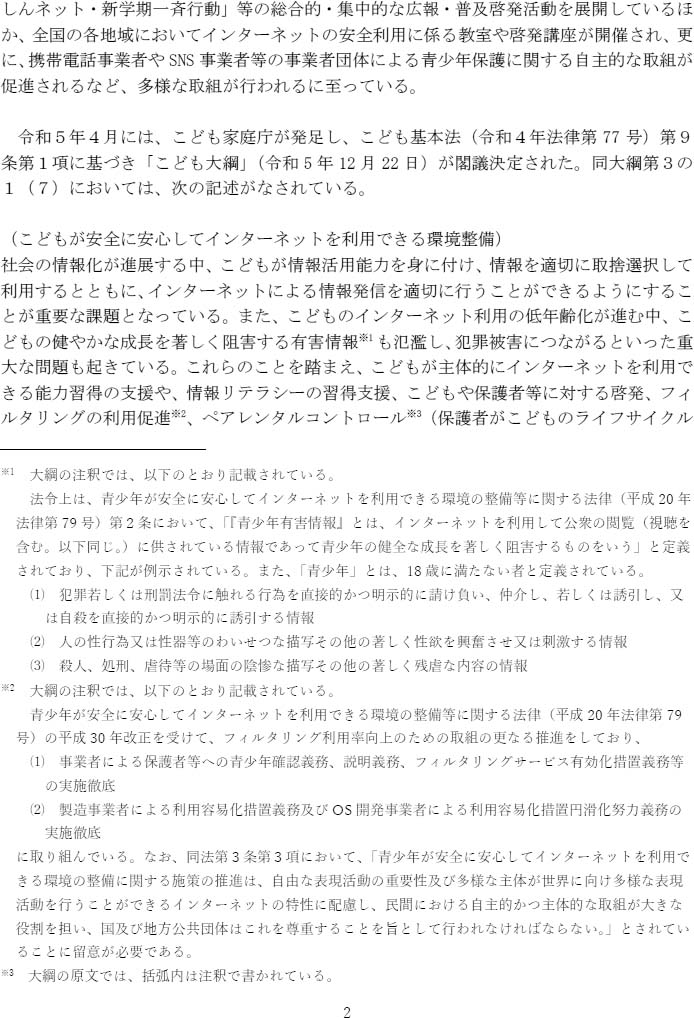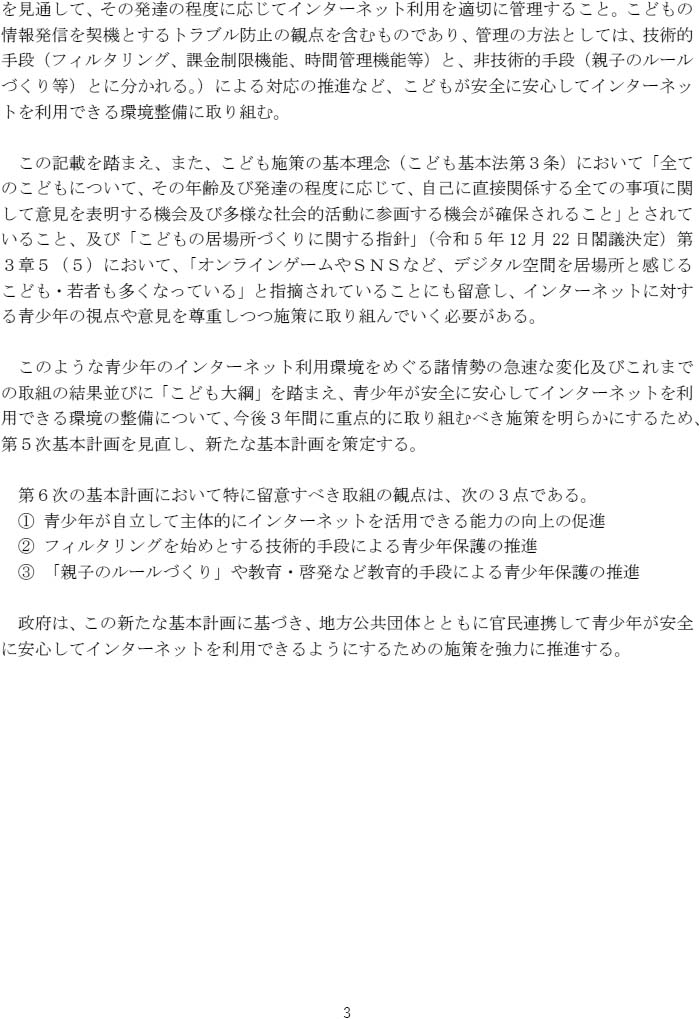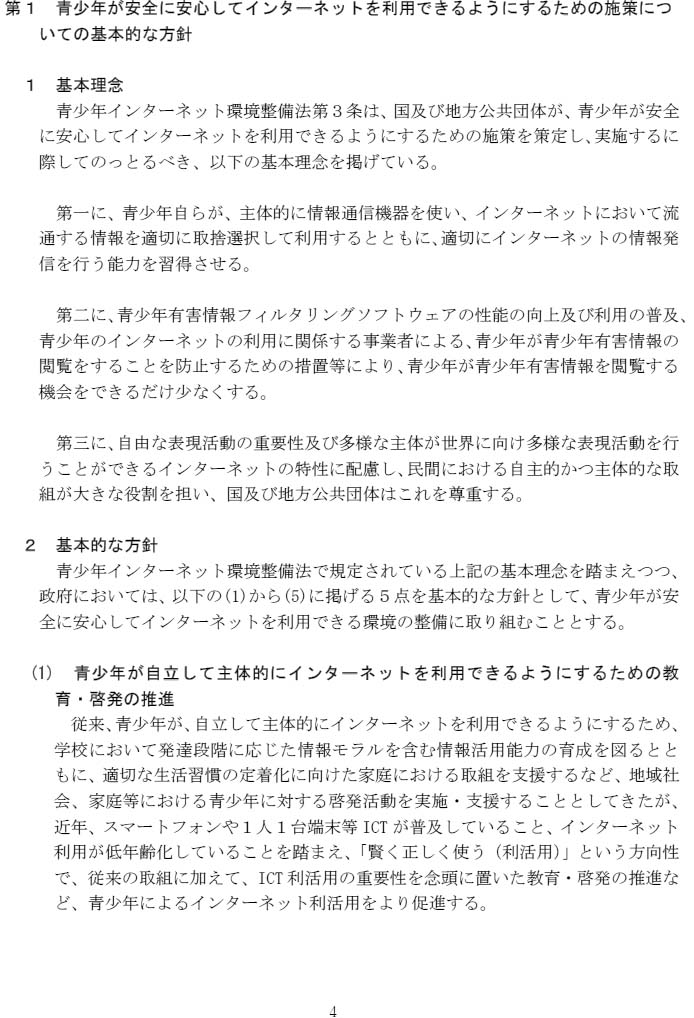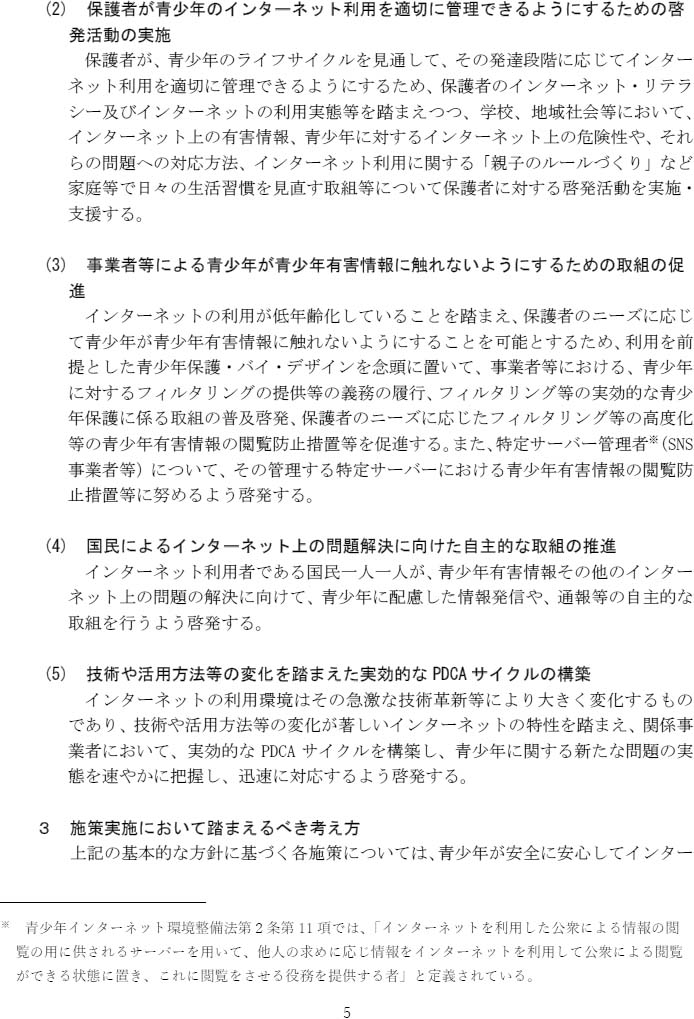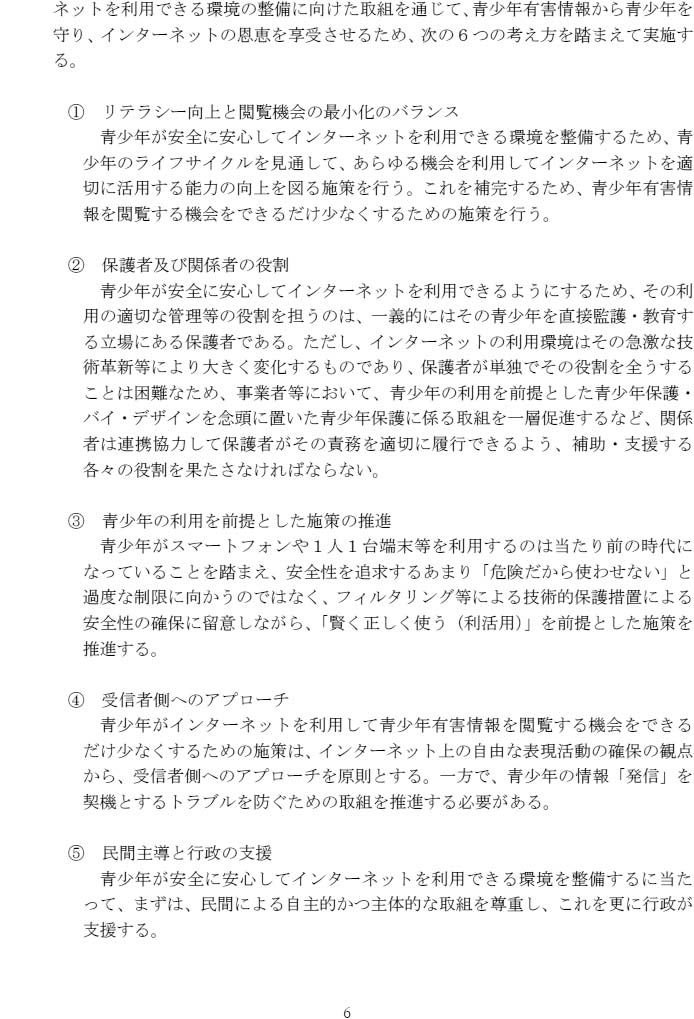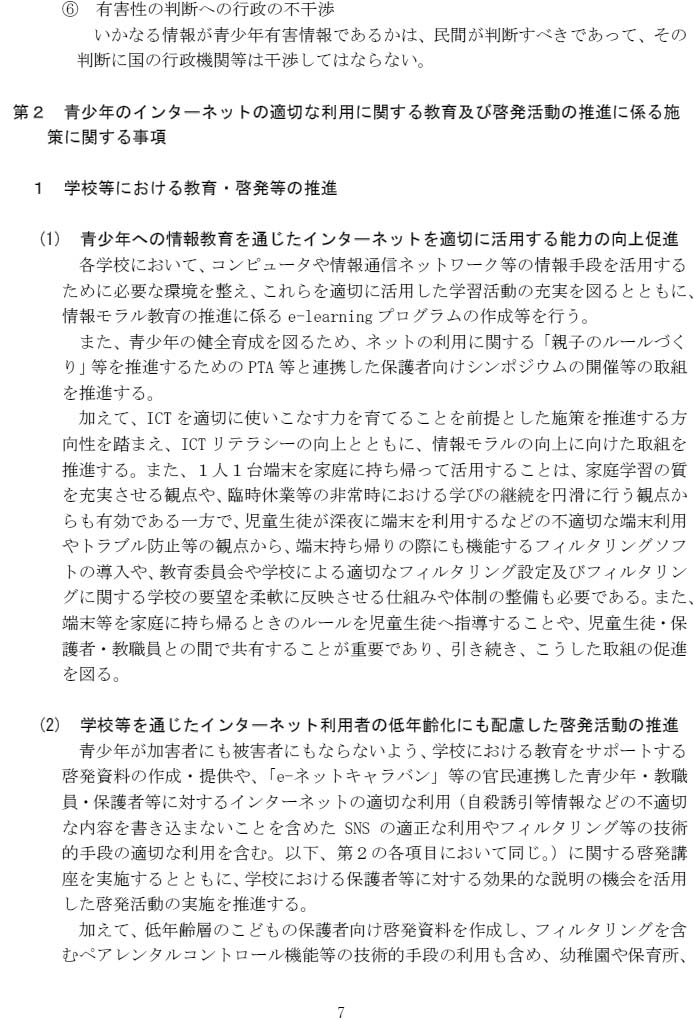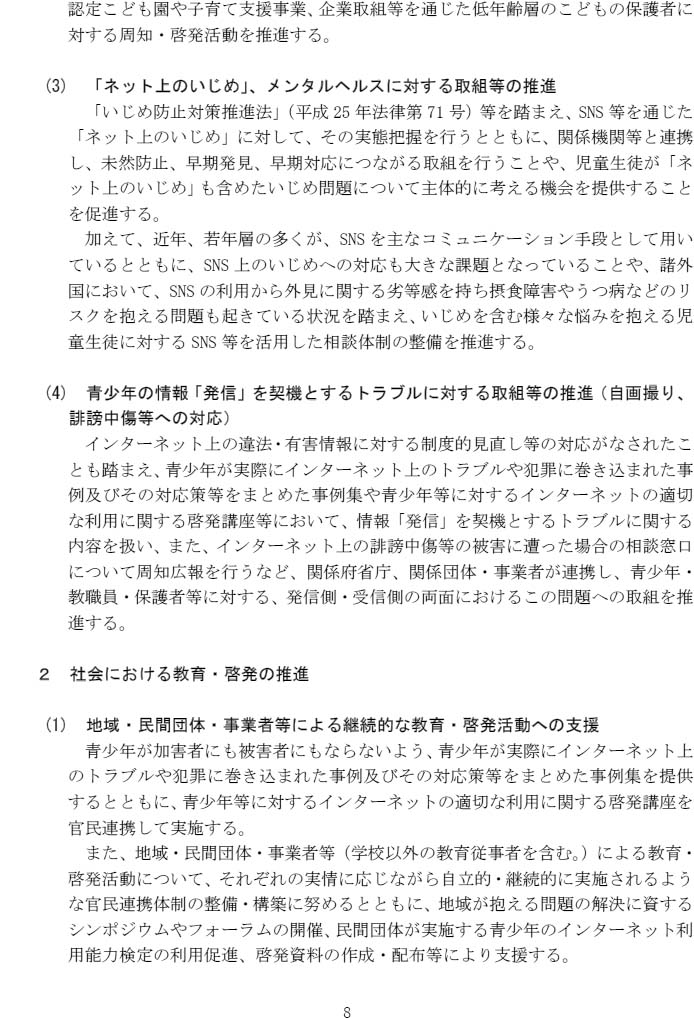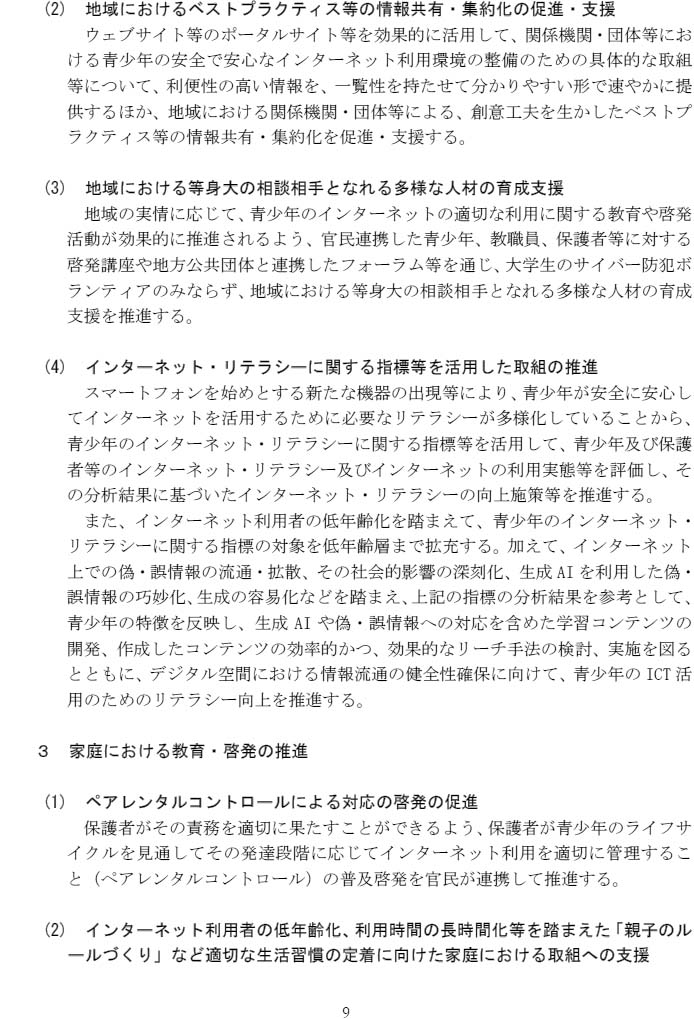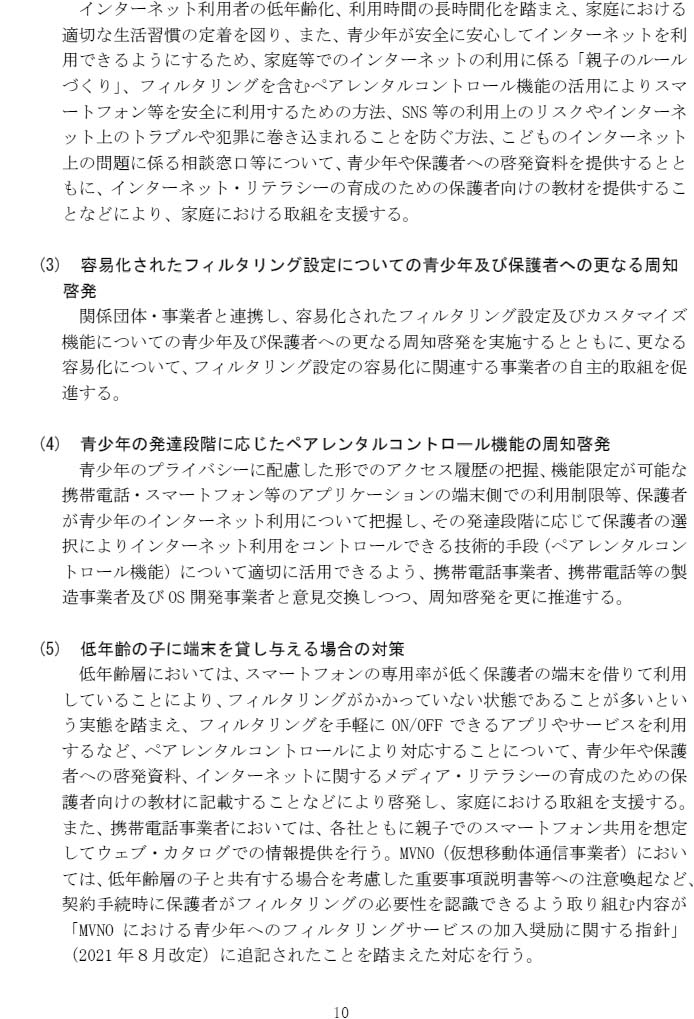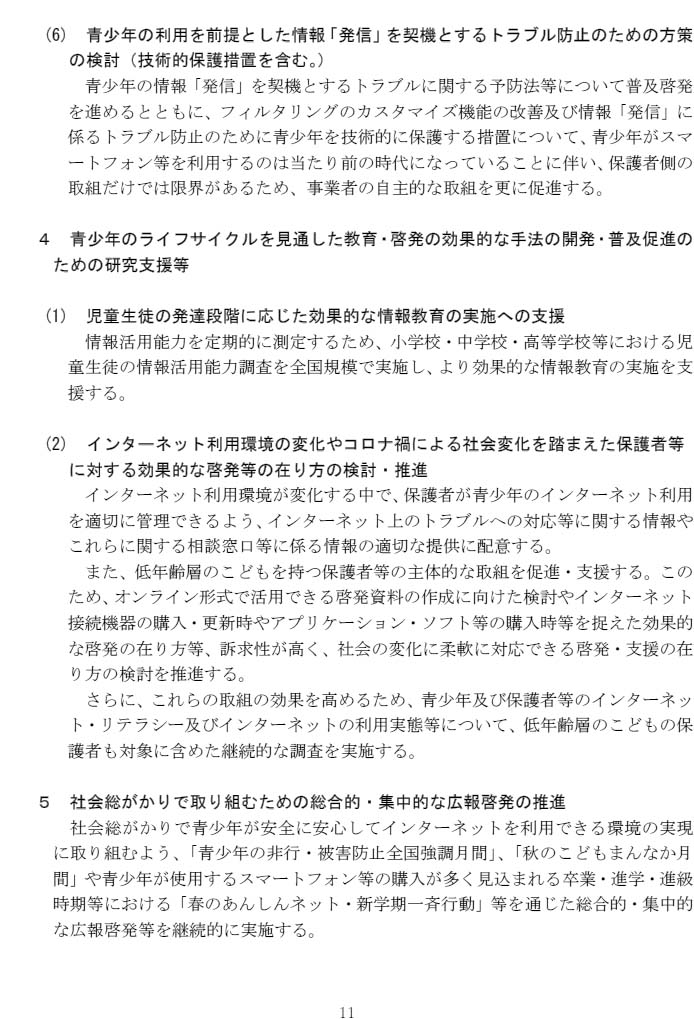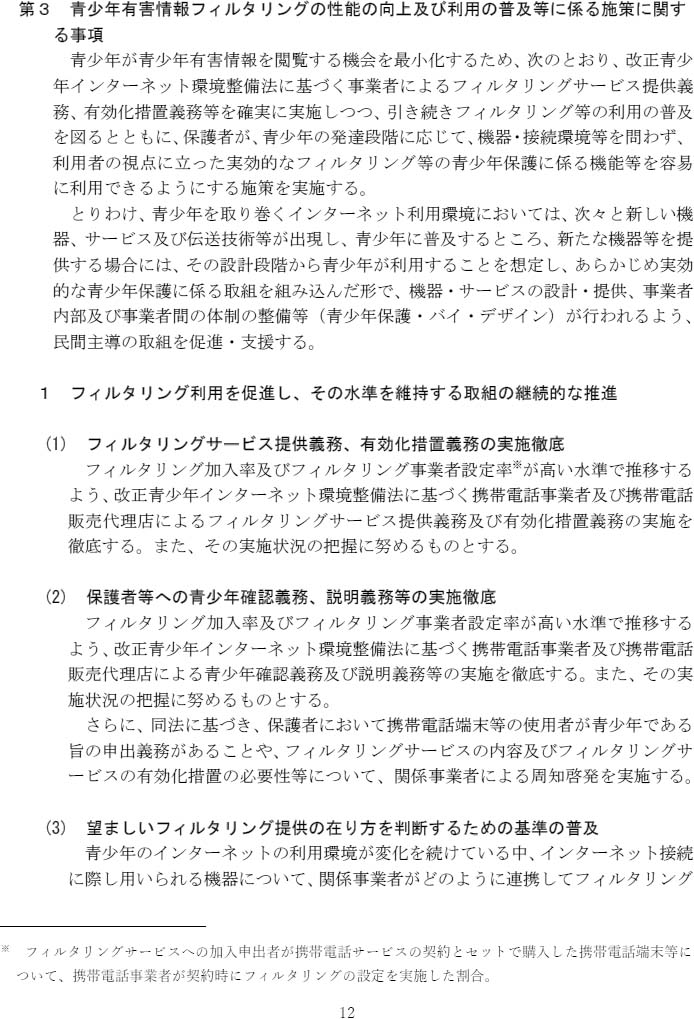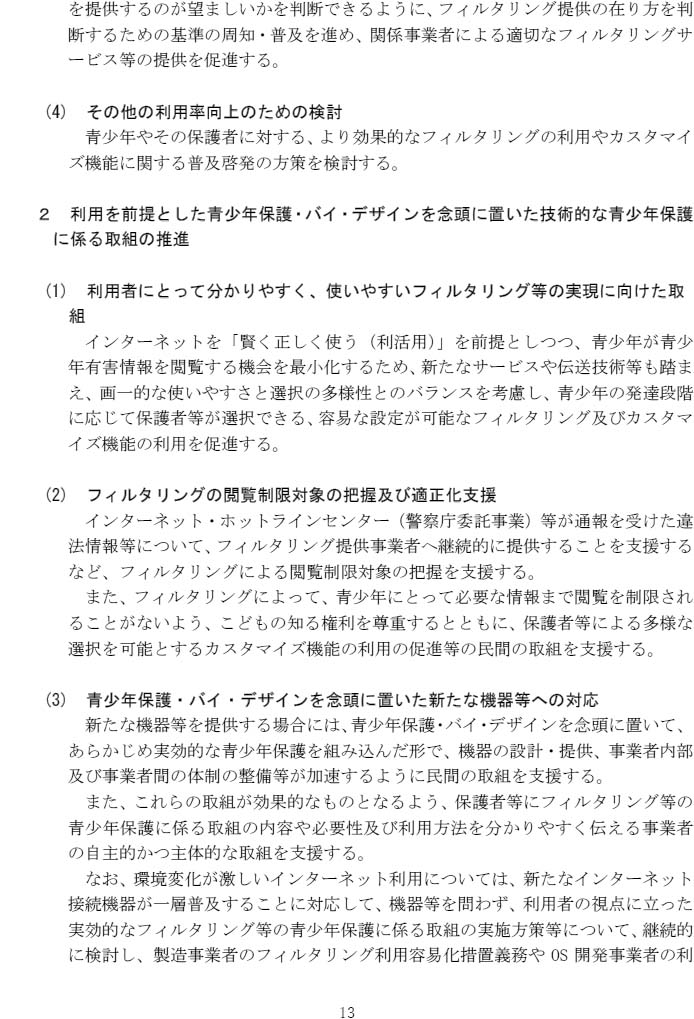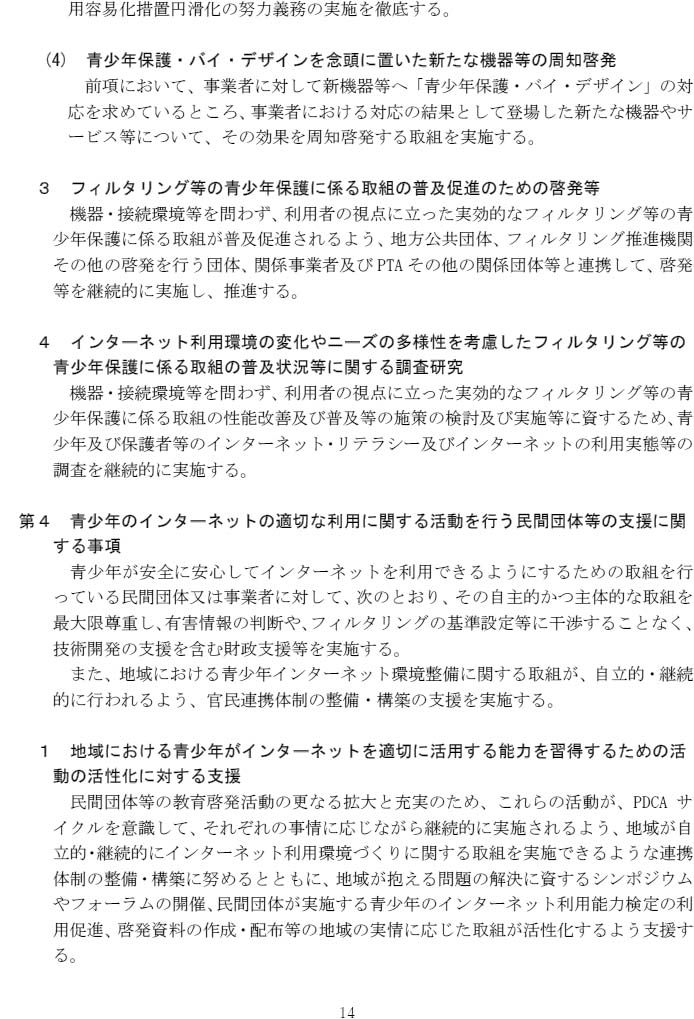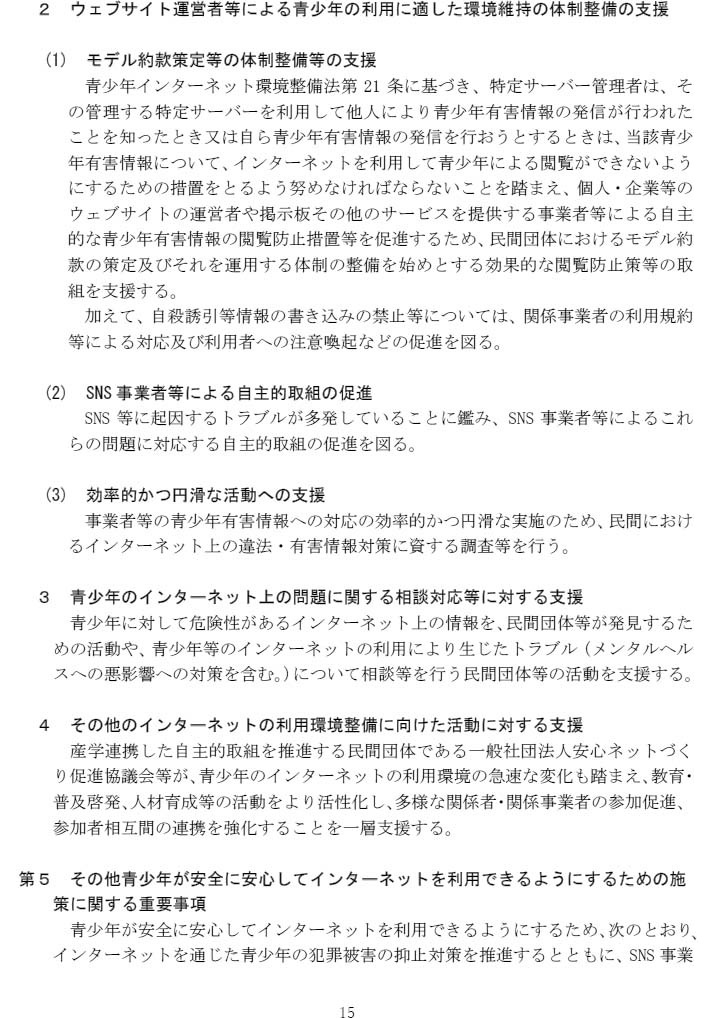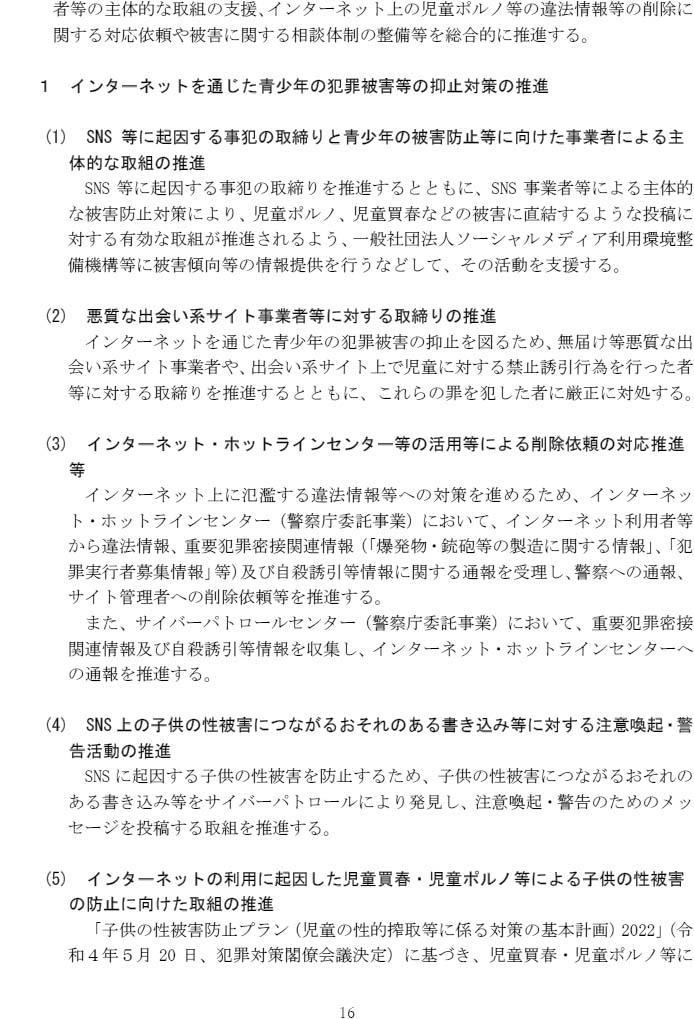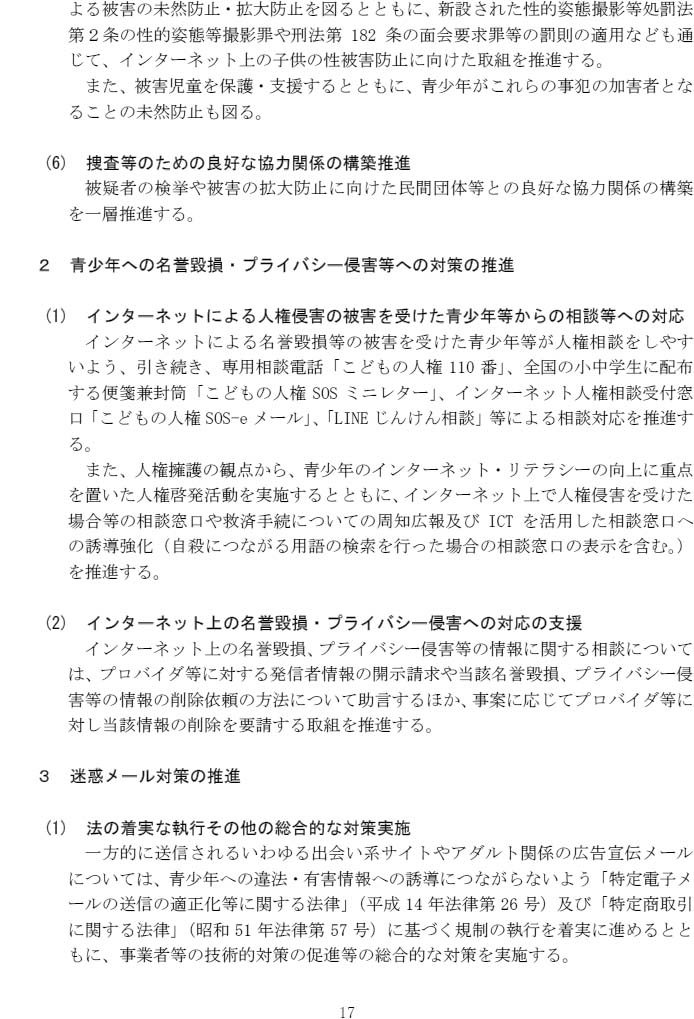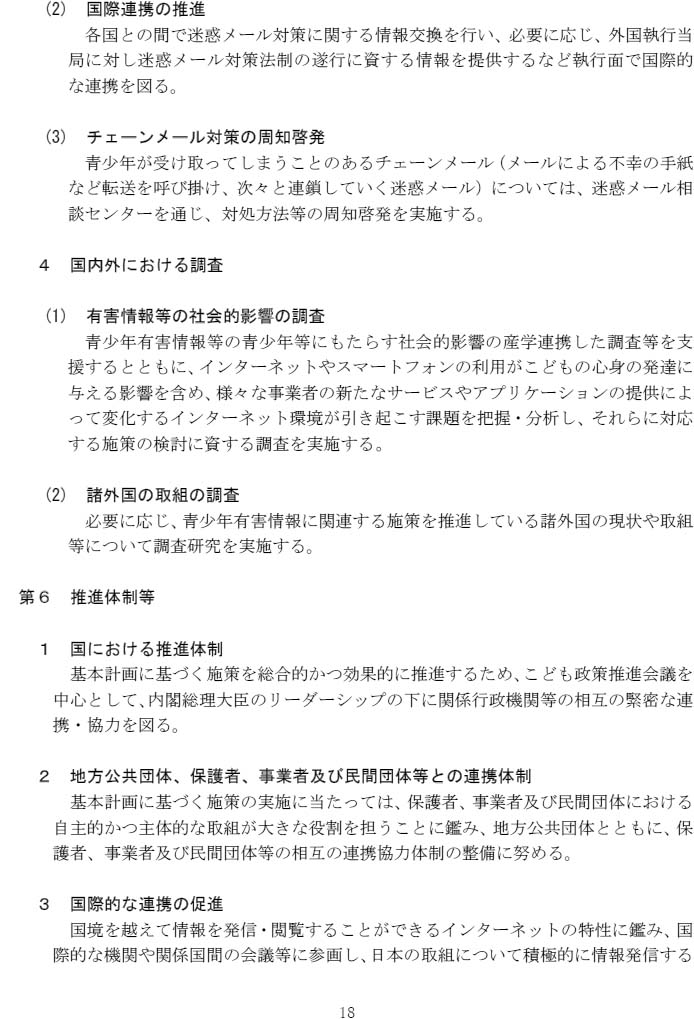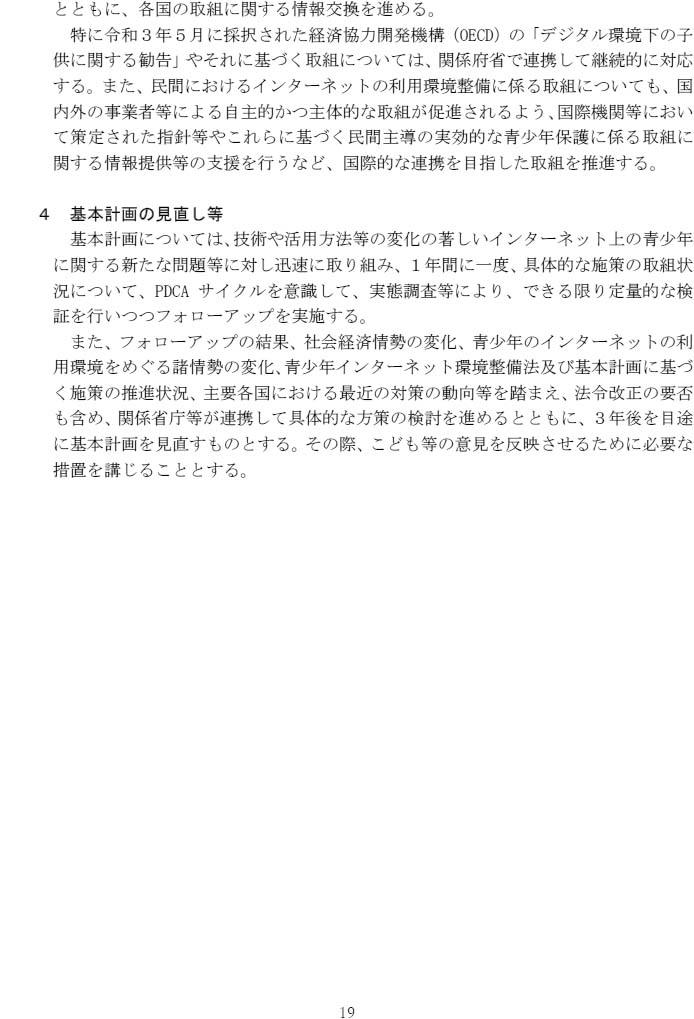○「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第6次)」に基づく施策の推進について(通達)
令和6年10月28日
達(少対、サ対)第489号
[原議保存期間 3年(令和10年3月31日まで)]
[有効期間 令和10年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和6年10月28日から施行することとしたので、効果的な施策の推進に努められたい。
なお、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第5次)」に基づく施策の推進について(令和3年7月28日付け達(少対、生環)第258号)は、廃止する。
記
1 趣旨
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下「法」という。)第8条に基づき、本年9月9日、内閣総理大臣を会長とするこども政策推進会議において、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第6次)」(以下「基本計画」という。)が別添のとおり策定された。
基本計画の見直し概要、施策推進上の留意事項等については、次のとおりであり、関係機関・団体と連携し、基本計画に基づく各種施策を効果的に推進しようとするものである。
2 見直し概要
(1) 今後の取組の方向性
基本計画の「はじめに」において、「青少年が自立して主体的にインターネットを活用できる能力の向上の促進」、「フィルタリングを始めとする技術的手段による青少年保護の推進」及び「「親子のルールづくり」や教育・啓発など教育的手段による青少年保護の推進」を特に留意すべき取組の観点として挙げている。
(2) 警察関連の主な見直し内容
ア SNS上の子供の性被害につながるおそれのある書き込み等に対する注意喚起・警告活動の推進【基本計画第5―1―(4)】(一部見直し)
SNSに起因する子供の性被害を防止するため、子供の性被害につながるおそれのある書き込み等をサイバーパトロールにより発見し、注意喚起・警告のためのメッセージを投稿する取組を推進する。
イ インターネットの利用に起因した児童買春・児童ポルノ等による子供の性被害防止に向けた取組の推進【基本計画第5―1―(5)】(一部見直し)
「子供の性被害防止プラン(児童の性的搾取等に係る対策の基本計画)2022」(令和4年5月20日、犯罪対策閣僚会議決定)に基づき、児童買春・児童ポルノ等による被害の未然防止・拡大防止を図るとともに、新設された性的姿態撮影等処罰法第2条の性的姿態等撮影罪や刑法第182条の面会要求罪等の罰則の適用なども通じて、インターネット上の子供の性被害防止に向けた取組を推進する。
また、被害児童を保護・支援するとともに、青少年がこれらの事犯の加害者となることの未然防止も図る。
3 施策推進上の留意事項
(1) 青少年のインターネットの適切な利用に関する啓発活動の推進
ア 知事部局や教育委員会、学校、サイバー防犯ボランティア等の関係団体、携帯電話インターネット接続役務提供事業者及びその契約代理店(以下「携帯ISP(インターネット・サービス・プロバイダ)等」という。)等と連携しながら、非行防止教室、進学・進級時における保護者説明会、サイバーセキュリティに関する講習等あらゆる機会を捉え、児童・生徒、保護者、学校関係者等に対し、可能な限り最新で具体的な事例に基づき、インターネットの利用に起因した青少年の犯罪被害や非行を防止するための対策等の情報提供を行うなど、インターネットの適切な利用及びフィルタリングを含むペアレンタルコントロール機能の普及促進のための広報啓発活動を推進すること。
なお、広報啓発活動の推進に当たっては、インターネット利用者の低年齢化にも配意すること。【基本計画第2―1―(2)、第2―2―(1)、第2―3―(1)・(2)・(3)・(4)、第2―4―(2)、第2―5、第3―3】
イ 青少年に急速に普及しているスマートフォンは、携帯電話回線に係るフィルタリングのほか、無線LAN回線に係るフィルタリングや、青少年有害情報の閲覧を可能とする出会い系やアダルト系等のアプリケーションに係るフィルタリングの設定・管理が必要である。特にスマートフォン向けの標準的なフィルタリングソフトウェアでは、青少年の学齢に応じたフィルタリングの強度や利用時間の設定ができることや、利用を許可又は制限できるアプリケーションについても容易に個別設定できること等を青少年の保護者に対して周知させること。また、スマートフォンのほかにタブレット端末、携帯ゲーム機、携帯音楽プレーヤー等の青少年が利用する機器に応じた適切な管理方法等が必要であることから、これらについて、具体的で分かりやすい説明に配意すること。【基本計画第2―3―(2)・(3)、第2―5、第3―3】
ウ 地域の実情に応じて、青少年のインターネットの適切な利用に関する教育や啓発活動が効果的に推進されるように、少年警察ボランティア等に対して、具体的な児童被害の実態を情報提供するなどして、人材の育成・活動を支援する取組を推進すること。
なお、サイバー空間における規範意識の改善へ貢献することが期待できるサイバー防犯ボランティアの育成・活動を支援する取組を引き続き、推進すること。【基本計画第2―2―(3)】
(2) フィルタリング利用率向上のための取組の更なる推進
ア 法に基づく、携帯ISP等による青少年確認義務、フィルタリングサービス説明義務、フィルタリングサービス有効化措置義務等が徹底されるよう、管内の携帯ISP等に対し、継続的に指導・要請すること。【基本計画第3―1―(1)】
イ 青少年有害情報の閲覧やSNS等に起因する福祉犯等の被害を防止するため、プロバイダ等関係事業者に対して、青少年に対するフィルタリングの提供の促進等を呼び掛けること。【基本計画第3―1―(1)】
(3) インターネットを通じた青少年の犯罪被害の抑止対策の推進
ア インターネットを通じた青少年の犯罪被害の抑止を図るため、SNSに起因する事犯、出会い系サイト上の禁止誘引行為、インターネット上の児童ポルノ事犯等サイバー犯罪の取締りを推進するとともに、これに必要な取締体制の強化に努めること。【基本計画第5―1―(1)・(2)・(5)】
イ SNSに起因する子供の性被害を防止するため、子供の性被害につながるおそれのある書き込みをサイバーパトロールにより発見した場合は、少年女性安全対策課に報告すること。【基本計画第5―1―(4)】
ウ インターネット上の児童ポルノを把握した場合は、捜査上の支障が生じると認められる特段の事情があるときを除き、速やかに、必要最小限の証拠保全措置を執るとともに、少年女性安全対策課に報告すること。【基本計画第5―1―(5)】
エ 被疑者の検挙や被害の拡大防止に向けた民間団体等との良好な協力関係の構築を一層推進すること。【基本計画第4―1、第4―3、第5―1―(6)】
4 報告
基本計画に基づいて実施した活動等については、「犯罪抑止活動等報告管理システム」等により、少年女性安全対策課長に報告すること。
別添